-1024x576.jpg)

課題が多い、課題が終わらない、テスト前の提出期限が近い(ブツブツ…)

一貫くん、今日はずっと「体系数学」の問題集と格闘してるよね?

使ってる問題集は…「発展編」の方ね、問題量も多いから計画的に進めていかないとダメだよ

そういえば、私が使ってる「標準編」の問題集とは問題数が違うね
うわっ、この「C問題」とか解けなさそう💦

後半の難易度やばいでしょ、今回の定期テストは副教科は捨てるしかないかも…
「体系数学」は中高一貫校のために生まれた数学テキスト
「体系数学(数研出版)」とは多くの中高一貫校で採用されている、数学の検定外テキストです。普通の教科書も配られますが、ほぼ開かれることはありません。

7割方の学校が「体系数学」採用かな、ほかにも「システム数学(啓林館)」「数BEKI(教育開発)」を採用している学校もあるよ
.jpg)
「新中学問題集(教育開発)」を採用している学校もありますが、これは検定教科書と同じ配列です
いわゆる検定教科書が、文科省設定のカリキュラム(学習指導要領)に準拠しているのに対し、「体系数学」は中高6年間を通して教育できるメリットを活かせるよう、単元の内容と配列に独自の編成がなされています。
例えば「一次方程式(中1内容)」の次に「連立方程式(中2内容)」、そして「不等式(高1内容)」を中学1年生の間に連続して学習します。また中学数学の単元でありながらも、部分的に高校内容が配置されていますので、内容のボリュームだけでも、公的カリキュラムの1.3倍ほどあります。
加えてほとんどの中高一貫校は2年~2年数か月間で、中学数学の内容を終了させますので、相対的なボリューム感は一層増すでしょう。

つまり中高一貫校の「数学」という教科は、「体系数学」の採用によって間違いなく大変になっています
確かにやや緩めの設定にされている中学数学と比べ、高校数学は(特に数学ⅢCが必修の理系は)質・量ともに傾斜が大きくなります。生徒たちの心身も成長しますが、それでも負担感は5倍増しともいわれます。
その結果、高校では「苦手な数学は選択せず、英語と社会に全振りする」なんて戦略が、トップレベルの私大でも当たり前のように行われています。
そういった大学受験情勢を見越して、中学数学とのバランスを取り、前倒しで高校数学に取り組めるのは、確かに有効な戦術といえるでしょう。そして「体系数学」はそのニーズをよく反映して構成されていますので、相性抜群です。

高校受験を経由しない中高一貫校だからこそ、効率的に授業ができるんですね!
_20241107_132651_0000.png)
ところがどっこい、”効率性”とはよく切れる諸刃の剣なんだ
.jpg)
”効率性”に置いて行かれて、全く前の単元が分かっていない相談もよく受けますね
体系数学の「標準編」と「発展編」について語る(ややオタク向け)

塾長はけっこう「体系数学」という教材が好きです
比例のあとに一次関数なんて設計も覚えやすいですし…
.jpg)
僕も参考書オタクなんで、分かる気がします
ビバ!青チャート!数研出版!!
体系数学は「代数編」と「幾何編」に分かれます。そのため、授業や定期テストも2分野に分ける学校がほとんどです。
また各々に傍用問題集「体系問題集」があり、定期的な提出課題になると同時に、教科書と併せて定期テストの試験範囲となります。学校外では教科書よりも、この体系問題集と向き合っている時間がほとんどでしょう。
さらに体系問題集は「標準編」と「発展編」に分かれています。
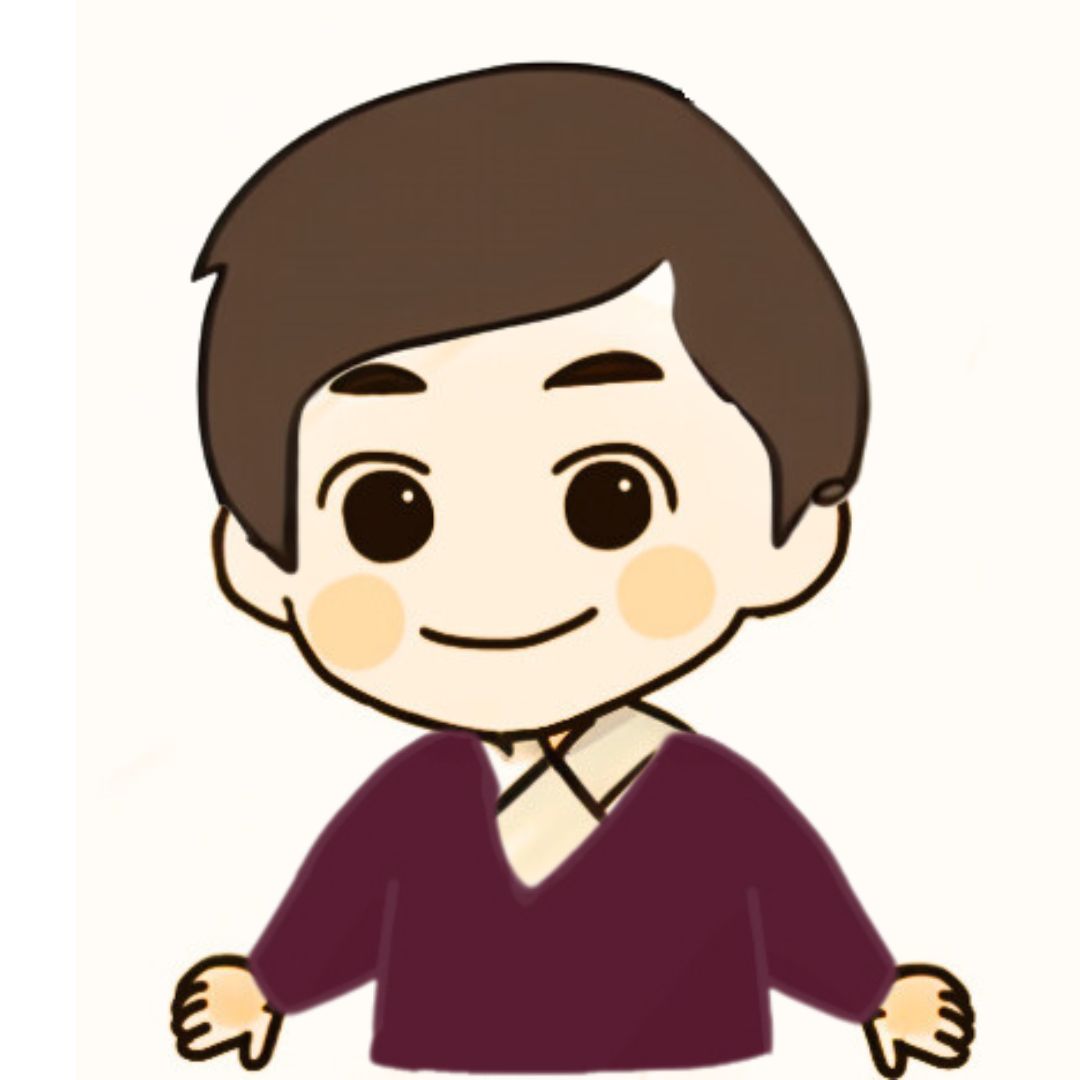
さらっと難易度を分類しましたが、この2種類は別物です
「発展編」採用校のキミは覚悟を決めた方がいいぞ!

うちは代数も幾何も「発展編」なんだ!
B問題からの計算量と複雑さがエグい、こんなに計算ややこしくして、何の意味があるんだ…

私が使ってる「標準編」にもB問題はあるけど、何か違うのかな?
「標準編」のB問題は、確かに表題に違わず、標準的な典型問題で構成されています。エクササイズとしてもちょうど良いものがそろっているように思います。もう少し練習したい場合は市販品の「チャート式体系数学」などを併用すると良いでしょう。
一方で「発展編」のB問題については、確かに典型問題もありますが、Bの後半〜C問題に至ると「計算のための計算」としか言いようがない、あえて複雑な計算式に設定してあるものが頻出します。
さらに問題数が多いので、見開き2ページをこなすのに2時間かかった、なんてケースもざらにあります。
保護者の方は「なんで全然進んでないの!」って怒らないでくださいね。1問2分かかる問題は、50問で100分。加えて計算ミスの直しなど、どこで自分が間違ったかのチェックもかなり大変なのです。

C問題とか総合問題はやらなくていいって学校もあるのに、うちは全部、全部です
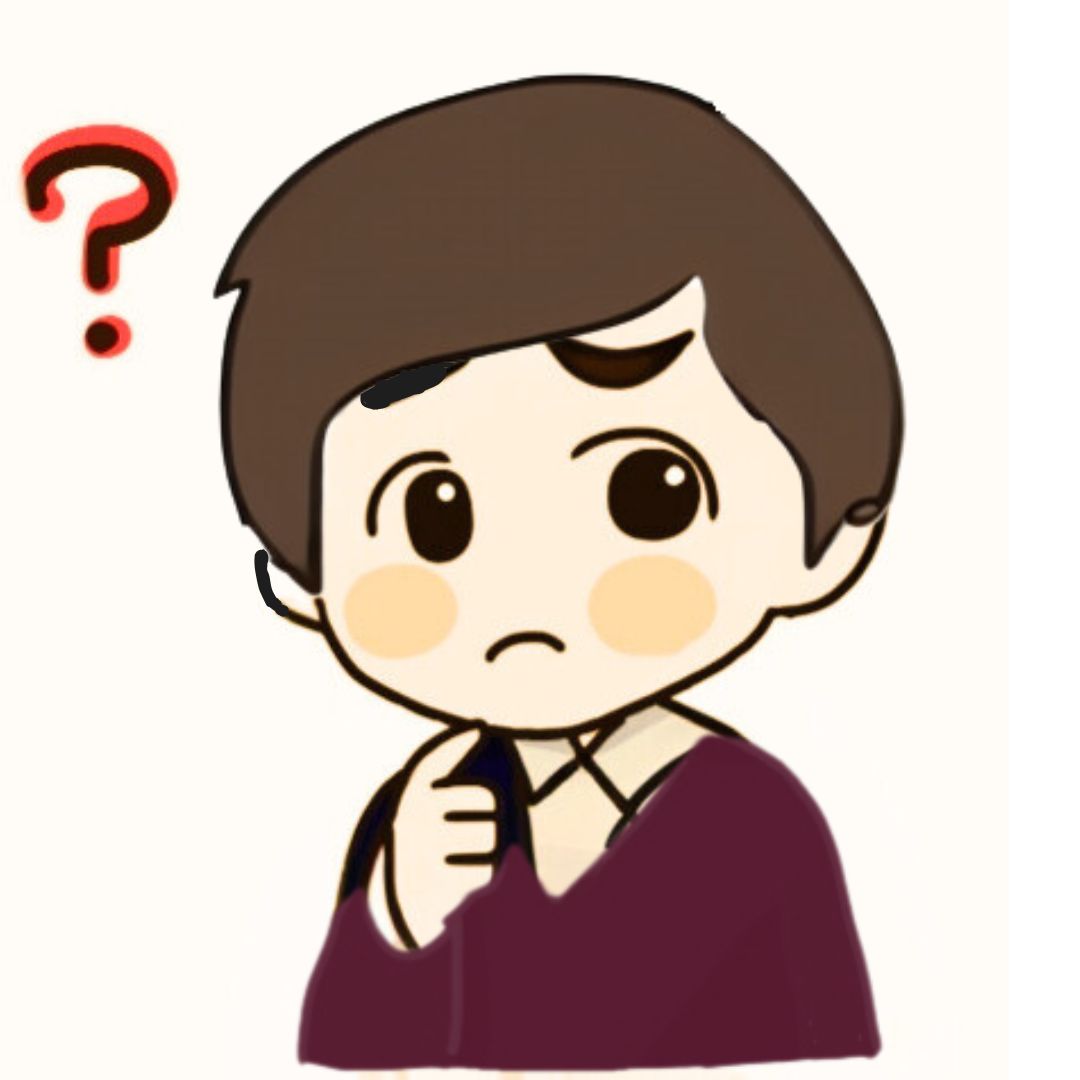
都立中高一貫の方が容赦がないような気がするのは、塾長もまだ未解決です
数学を含めて、課題に埋もれてしまいそうな時があるからね
体系数学のご利用は計画的に!
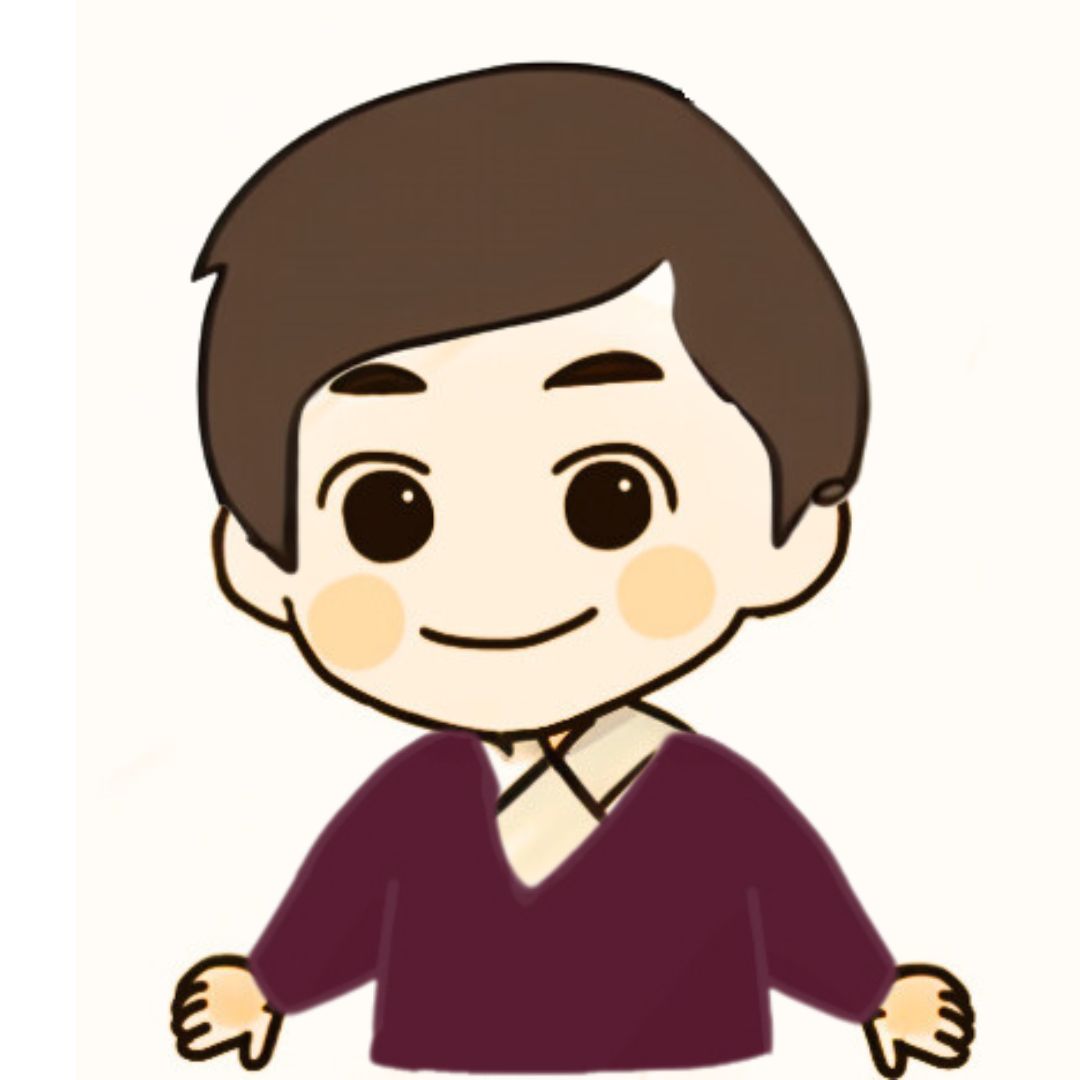
一貫くん、ちょっと勉強の予定を調整するから、僕のところにおいで!

はい、お願いします…
一貫くんは、都立中高一貫校に通学しています。
都立中高一貫校の多くは3学期制を採用しており、1学期と2学期は「中間テスト」「期末テスト」が2回ずつ、3学期には「学年末テスト」が1回の、計5回の定期テストが1年間のうちに実施されます。
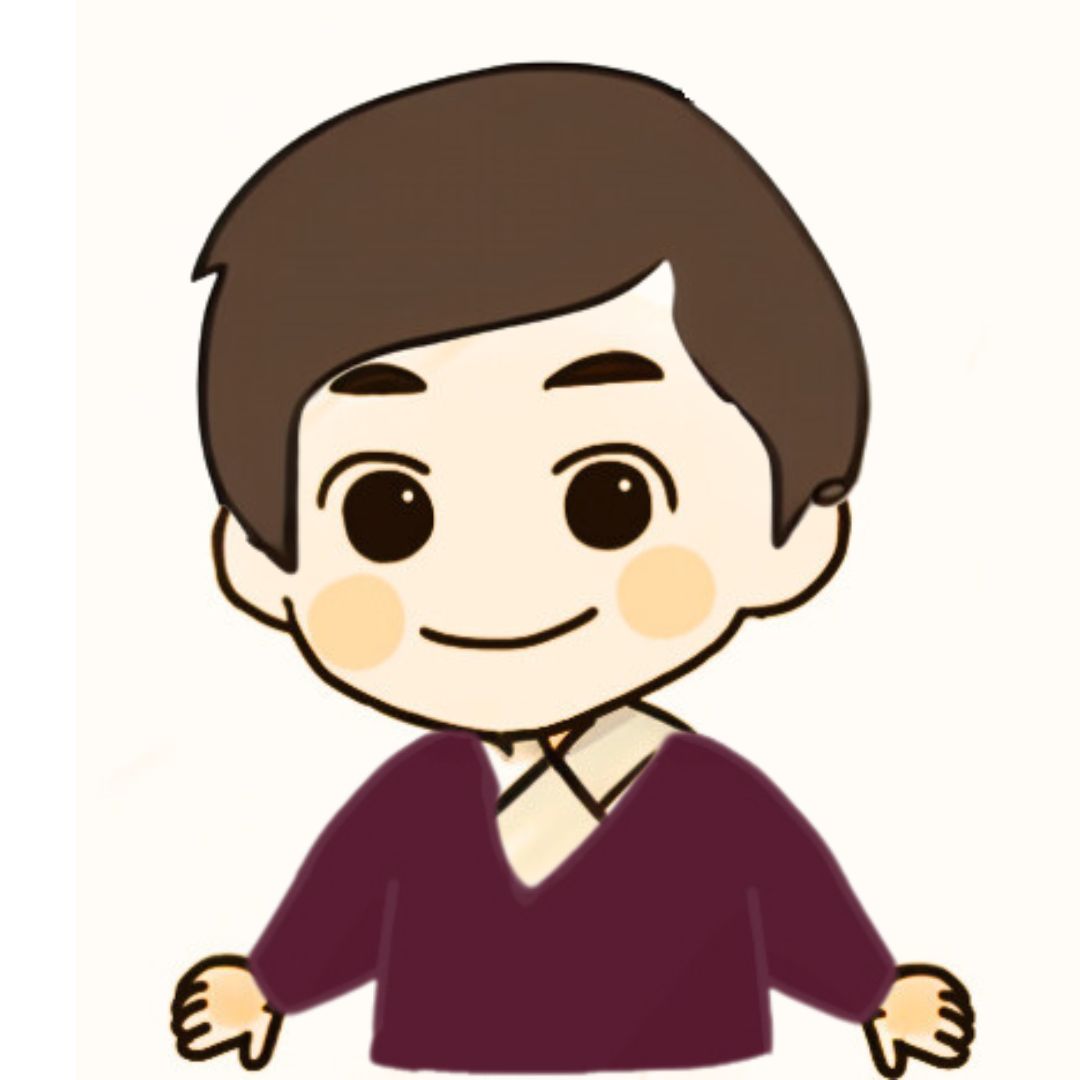
1年間は12か月だけど、夏休みや冬休み、春休みもあるから、実質10か月くらいだよね

そう思うと1か月半~2か月に1回は定期テストがめぐってくる計算なのか…
テスト2週間前なんてあっという間に来てしまうね

その通り!
だからうちの塾では、定期テストが終わった翌週に次のテストの話しを始めてるよね
塾長の指導経験上、「体系数学」をお使いの皆さんは、「標準編」「発展編」を問わず、試験2週間前から課題に取り組んだり、テスト対策を始めても、まず間に合いません。
いえ、間に合わせることはできるかもしれませんが、テスト対策は「数学」しかやらなくてもいいのですか?
歴史の年号や元素記号も怪しいのに、数学の計算や証明をやり続けても大丈夫ですか?「体育」や「家庭科」とかの副教科はもちろん捨てますよね?
塾長としては塾で受講している教科以外だって、大学受験の備えになるようできれば頑張ってほしいんです!高校受験生みたいに、内申点が関係なくても!(まあ副教科は大体でいいですが…ボソボソ)
.jpg)
塾長、落ち着いて!
一貫校でない公立中学校だって、2週間前スタートだと結構厳しいんですよ

確かにお兄ちゃんも副教科の内申点が伸びなくて、都立高校のランクを下げたっていってたな…
テスト範囲が明示される2週間前という時間は物理的に足りません。ではいつからならいいのか?
塾長の結論は「6週間前~8週間前」です。
すなわち、定期テスト期間(テスト返却や解き直し提出期間を含む)が終わったらすぐ、です。
すぎに次のテスト該当範囲を予測をつけて、その先取り(予習)を始めるのが望ましいです。
もちろん数学は独学が大変な教科なので、中高一貫校の事情が分かる信頼できるコーチがいればベストです。

教科書の演習問題や体系問題集の「B問題」以上は、講師と一緒に丁寧に解いた方が効果的です

先生が問題のポイントを力説してくれるから、同じような問題を解けることが増えました!
土曜日か日曜日のどちらかには、必ず3時間程度の”自分のための”自習時間を設定して、体系問題集の消化を始めましょう。問題集の何番まで解けば良いかは、学校か塾の先生に相談すると良いでしょう。
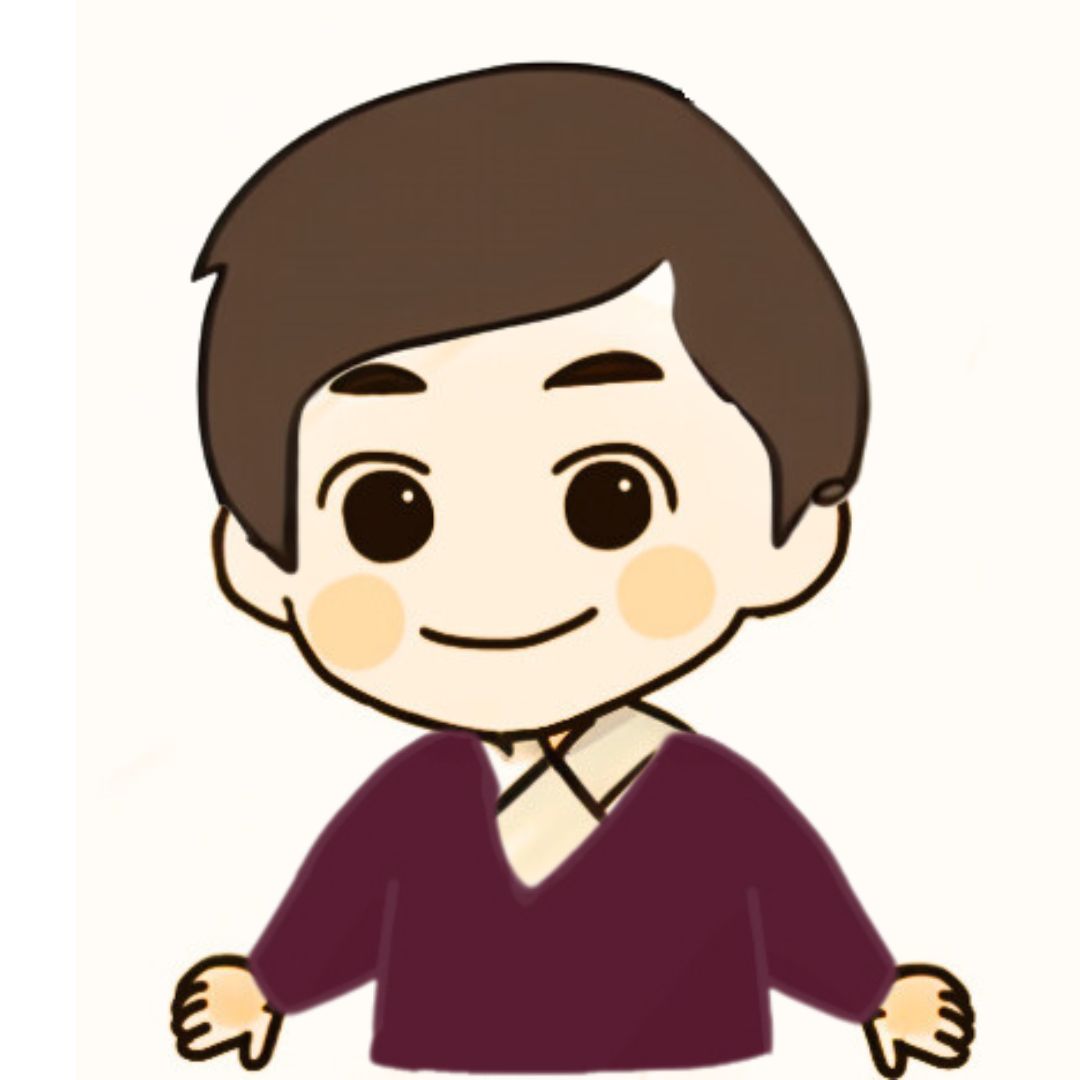
うちの塾では2週間前に提出課題が終わっている状態を目標にしています。
.jpg)
それでも授業や自習では、かなり頑張って間に合わせてるよね
_20241107_132651_0000.png)
いやはや、本当に中高一貫校のテストスケジューリングは厳しいんです…
学年が上がると内容も難しくなるからね、特に「幾何編」!
2週間前が見えたら、気になる他の教科の暗記学習なども手をつけつつ、「体系数学」は解き直しスタートです。
全部をやり直すのではなく、①自力で解けた問題、②解説を聞いて解けた問題、③解説を聞いてもピンときていない問題、に区別して、特にB問題をスラスラ解けるまで重点的にやりましょう。
計算ミスを含む間違いの癖や、概念的な理解の不足については、学校や塾の先生に適宜客観的な助言をもらってください。
「君はここを間違える傾向がある」と言われたところは、テストで実際にやらかす可能性が半々レベルです。
100点を阻止するためのような、難しい問題も出ます。一部の附属校や都立一貫校など、高校生レベルの難しい問題を好んで出す先生もいます。
「(テスト時間を考えても)解けない問題を解ける必要はない」というのが塾長の方針です。
でも9割方の生徒さんにとって、平均点プラス10点~20点を取るために解く必要のある問題は、難問・奇問の類ではありません。

「授業でやったよね、何度も言ったよね」、そんな問題を解いてテストを終えてほしいんだ
数学は時間のかかる教科です。付属の解説本を読んでも、「???」になることは普通にあります。
そんな教科をできる限り”効率的”に進めようと欲しているのが、中高一貫校です。
もちろん同じ体系数学を採用していても、すべての学校が「果ては東大か、医学部か」のようなハードなカリキュラムを敷いているわけではありません。
むしろほとんどの中高一貫校は自校の実態に合わせて、速度や範囲、レベルを調整し、きちんと勉強をした生徒がきちんと報われるようにテストを作成されています。生徒の大半を落ちこぼれにすることは、学校としても全く本意ではありません。
しかしその「きちんとやる」のハードルが思ったより高かった、という認識の甘さが「落ちこぼれ」や「深海魚」に至った生徒さんを生み出す背景にもつながっています。同じ学力層の生徒さんが集まっているのですから、成績の良い生徒さんは、やはりきちんと勉強しているものです。そんな素振りは見せないかもしれませんが。
中1の最初期から出会う「体系数学」を上手く乗りこなせるかどうかは、今後の勉強全体の在り方を占う試金石となります。現実と向き合って、それにきちんと対処しようとすることは、中高生の皆さんにとって少し背伸びをするような心持ちかもしれませんが、きっと皆さんを自身でも思ってもみなかったような可能性や出会いへ導いてくれると信じています。

お父さん、お母さん、学校や塾の先生など、大人の知恵もしっかり活用してくださいね!
打開策は人と話しているうちに見つかったりするものです!


-160x160.jpg)