-1024x576.jpg)

私は同じ私立校の小学部から中学部に上がりました
この塾には小学6年生の秋から通ってます
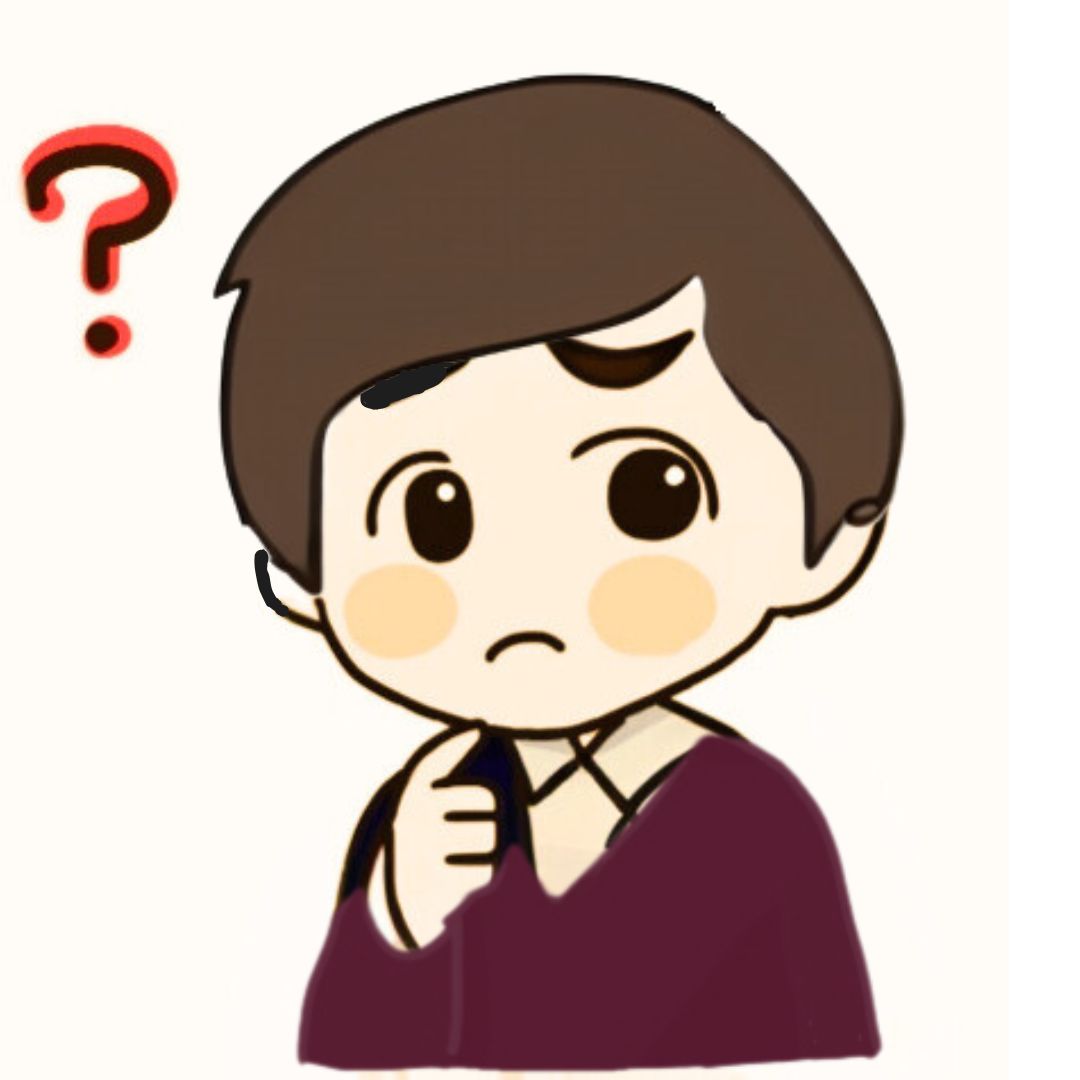
中学受験組(中入生)との学力差を中高さんのお母さんは心配してたね?

中入生は計算力とか文を読むスピードがすごくって!

僕も中学受験塾では大量にやったよ 16×16=256(いろいろにこむ)!
中学受験をするとは、どういうことなのか?
首都圏を中心に、中学受験が盛んですね。2024年度の受験率は22.7%となり、都内ではクラスの半分が中学受験をするなんて聞くと、「じゃあうちの子も中受を…」なんて周りに流されちゃいそうなのは、塾長だけではないでしょう。
少子化なんて何のその、「夏期講習で25万円!」なんて数字が飛び交う中学受験塾をうらやむばかりです。

高3生より全然高い!若手塾講師の月収より高いんじゃないか?
.jpg)
中学受験後は、うちの塾に来てくれることを祈りましょう…!
気を取り直して、話題を戻しましょう。
使うのはお金だけじゃない!人生の時間も(親子で)ガッツリ投資しているのです。
彼女(彼)らは小学6年生ですよ?それでも夏休みにやるべきことはプールでも、山でも、ゲームでもなく、「勉強」です。
アンビリーバブルですね。

中学受験大手塾サピックスの勉強時間の目安は、次のとおりです。
2年生:週2時間、3年生:週3時間、4年生:週4時間、5年生:週10時間、 6年生:週9〜12時間
特に小学5~6年の勉強時間に注目していただきましょう。
学校や塾の授業は省きますので、実際はもっと勉強しているはずです(上手くさぼっている子も多数でしょうが…)。
間違いなく気の抜けた高1、高2より勉強してますね。

私立・国立小学校は、公立小学校に比べれば、周囲の友人も真面目で、先生方の勉強に対する要求も厳しいですが、それでもバリバリの中学受験組には、その量も密度も比較にならないでしょう。
ここで結論ですが、中学入学時点において、内部進学組は中学受験組の学力と胆力にはかないません。

でも私だって狭き門の「小学受験」を突破したんだよ!あんまり記憶にないけど…
はい、内部進学組の中には凄いポテンシャルを持った方がいます。実は学年の上位層は中学受験組ではなく、内部進学の生徒たち数名が占めているとか、いないとか…。

サピックスα1(四谷偏差値70オーバー)にいたような人ね…

わずか5~6歳の幼児期に、その可能性を見抜く小学受験の試験官もすごいですね!
でも学力差は埋まります、安心してね!
.jpg)
私は高校受験して、大学受験もしたけど、中学受験の同級生には負けなかったさ!バレー部もガチでやったし!遊びの誘いを断ったことも一切なし!

いきおい主任がドヤってる!

主任みたいにエネルギッシュなタイプは、バリバリ活動した方が受験も上手くいくみたいだね!
塾講師としての経験上、中学受験で培った貯金を感じるのは中1~中2の前半までです。
計算力、漢字の読み書きや語彙、文章の処理速度、図やグラフの処理、歴史の知識など…使える道具がたくさんあります。
英語を除いて、中学受験の焼き直し的な内容もたくさんありますので、テストの難易度によっては、授業だけで80点くらい取れてしまう方もいらっしゃるでしょう。
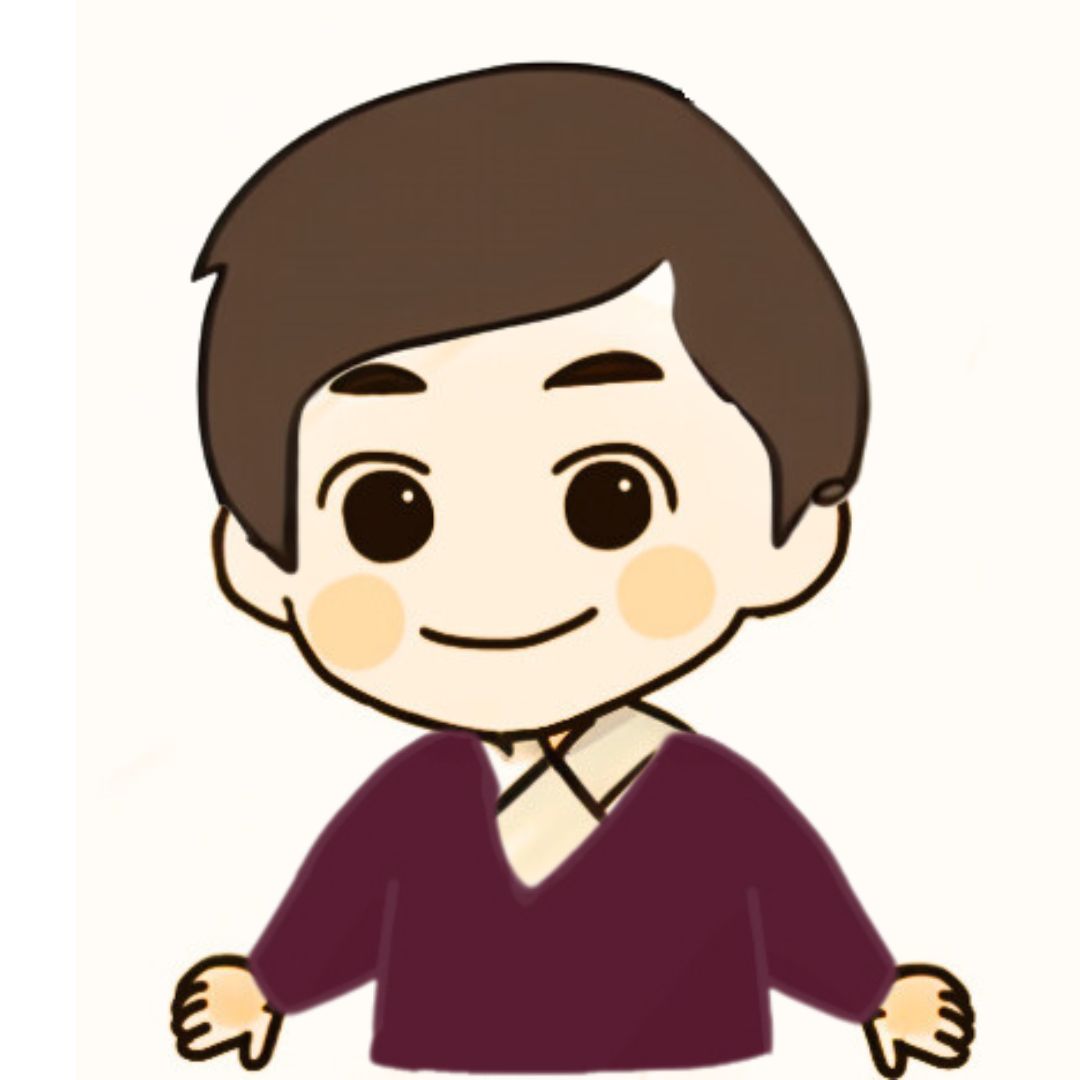
だいたい、そのあたりまでですね
あとは勉強しなければ、定期テストの度に点が落ちていきます

身に覚えがあります!
それでヤバいと思って、この塾に入ったんだもんなあ
中学受験は別に中学内容を先取りする勉強ではありません。学習内容のスタートラインは内部進学組と何ら変わりません。
中高一貫校生に先取りアドバンテージが生まれる大学受験とは、ここが決定的に違います。
すなわち足を止めてしまえば、確実に失速して「学校の先生が何を言っているのか、分からない」という、小学校では想像もしなかった状況に陥ることさえあります。
「勉強は勉強しないとできるようにならない」という当たり前の壁をきちんと認識しなければ、あっという間に黄色信号は赤信号に変わります。
中学1年生で”自立”しちゃいましょう!
中学1年生でやっておくべきことは、自分で勉強ができるようになることです。
多少口出しはされても、小学生のときのように、お母さんやお父さんに頼ってはいけません。

私の親はあまりうるさく言わなかったけど、私は小学生のときから自分で勉強してたよ

さすが御三家さん、努力も一種の才能だよね…
人から勧められた本、人から勧められたスポーツ、人から勧められたレストランを試してみて、それ自体が決して悪いものではなかったとしても、どことなく居心地が悪いように感じた経験はありませんか?
勉強についても同様です。親や学校の先生など誰かの期待に応えるためにやり続けても、たぶん数度目には空しくなります。良い点を取って新しいスマホでも買ってもらえれば、一時的には嬉しいかもしれませんが。
結局のところ、「学びとは自分事であり、自分にしかできないことだ」と良い意味でのエゴイズムを獲得した生徒から、急速に伸びていきます。勉強への当事者意識こそが勉強の密度、深さ、持続力を決めるからです。

数学が得意な子とか一日中幾何の難問を考えていたりするものね、しかも楽しそうに!
.jpg)
教育の世界だと、「内発的動機付け」なんてよく言いますね
そして誤解してほしくないのですが、「自立する」こととは「大人や指導者の手を借りないこと」と同義ではありません。むしろ塾長の経験上、ごく普通の生徒さんが一人の力で到達できる理解というのは、すごく限られたものになります。
客観的な現状把握と潜在的な可能性(ポテンシャル)の程度、長所と短所、必要な練習量や今後の見立てなど、案外と学習者自身が一番見えにくい立ち位置にいるものです。

我々は何かを通さずに、直接自分の顔を見ることはできないのです
卑近な例ですが、独力では60点までしかその力を出せなかった生徒が、信頼できる指導者を得て、80点、90点と点を伸ばしていくケースはたくさんありました。
その一方で、「自立学習」の名のもとに独習させられていただけの生徒が、理解不十分なまま平均点を割り続けているケースも多く見てきました。
自分のために、自分の力になってくれる指導者を見つけて、自分の勉強を頑張る、それは決して子供じみたワガママではありません。
文字や言葉という道具を得て、歴史の巨人たちの肩に乗り続けることで、人類はその叡智を広げてきました。
自分の背丈では見えなかった世界が見えるようになることに意義があるとするならば、自分の視野と理解を広げてくれる指導者は、ぜひとも探すべきだと塾長は思っています。

大谷選手と栗山監督の関係みたいなものかな?

スケールでかっ!

-160x160.jpg)